UNITY! 楽器図鑑
このコーナーでは、「UNITY!」のレコーディングで実際に使用された楽器について解説します。CDを聞きながら、「おっ、この音は」などと楽しむ際の資料として御活用下さい(一部の人たちにとっては、たまらない楽しさなのよね〜)。(^^;;
とくに今回は「サイバースペース」ということで電子楽器たちが大活躍しました(もちろんCDでは生楽器たちも同様に活躍しています)。下記のリストは音楽プロデューサーの"うしま〜く!"氏のみちくのスタジオにある電子楽器たちです。もちろんアルバムで使用されています。詳しい解説を"うしま〜く!"氏からしていただきましょう。
以下、"うしま〜く!"談
【Synthesizers/Keyboards】【Other Instruments】【Recording Equipments】
Keyboard:
ROLAND D-70
ROLAND S-50
ROLAND JUNO-6
Fender CHROMA Polaris II
Kurzwell Ensenble Grande MK-III(Master Keyboard)
YAMAHA DX-7
YAMAHA P-150(Digital Piano)
YAMAHA YC-45D(Combo Organ)
KORG POLY-61
SOLINA Strings Ensemble
ARP 2600
EMS AKS
SoundModule:
ROLAND SC-88(SoundCanvas)
ROLAND MV-30
YAMAHA TX-81Z
E-MU Vintage-Keys
AKAI CD3000
【Synthesizers/Keyboards】
現代のシンセサイザーには様々な種類があります。それぞれに用途があるとは言い切れず、何にでも対応できるようなモノがひしめき合っていますが、私は個人的にはそういったオールインワンで何でも出来るタイプのものはほとんど持たない主義です。従って「品川みちくのスタジオ」にある機種は、古いアナログタイプからそれほど新しくないデジタルタイプまでありますが、それぞれに用途別に使い、個性を尊重しています。
・ROLAND D-70 
「Peter宮崎道スタジオ」では比較的新しい方のデジタルシンセサイザーです。CDで使っているサウンドは広がりのあるサウンドやパイプオルガン、ブラスセクション等、比較的“音がいっぱい鳴っている”ようなサウンドに使用しています。「踊らずにはいられない」や「パラダイス」でのブラスサウンド、「きよきあさに」でのパイプオルガンサウンドなどは自らプログラミングしたサウンドをこのシンセから出しています。
《みちくの余談》
ROLANDは“LAシンセシス”(線形合成)という方法を打ち出したD-50を1987年に発表しました。このD-50がROLANDにとって初のフルデジタルプロセッシングのシンセサイザーでしたが、ストリングスやピアノなどのサウンドの効果的なシンセシスのため、アタック部分のみの1ショット/1ループ波形を多数内蔵し、他はアナログシンセをデジタル・プロセッシングに置き換えたようなシンセ波形をフィルタリングする「ハイブリッド型」の格好をしていました。そのため、同社のS-50並のクォリティの高いストリングスサウンドやエレピサウンドが得られ、個人的には大変悔しい思いをしましたが、このシンセは開発段階で色々と乗り越えられなかった発信機部分の不都合があったようです。しかし皮肉なことにその不都合が逆にこのシンセサイザーを特徴づけていたのです。これに続く下位機種であるD-20、D-10も同じような心臓部を持っていて面白い音が出ましたが、LAシンセシス・Dシリーズの最上位機種として登場したのがD-70でした。同社のプリセットサンプラーU-220にシンセサイズ機能をプラスしたような格好の“スーパーLAシンセシス”と言われるグレードアップした心臓部を持って登場しました。これが驚く程の倍音成分を含んだシンセ波形を作ることができましたが意外とつまらないもので、明らかに当時コルグの超大ヒットシンセ=M1の対抗機種という色合いが強いシンセでした。スタンダードサイズの61鍵より多い76鍵を持ち、MIDIマスターキーボードとしての機能が充実していたため、これを使っていたミュージシャンは2台目のマスターキーボードとして使っていたようです。Dシリーズの最上位機種であったハズが、皮肉な結果に終わってしまったと言えます。しかしUシリーズで大好評だった高品位な波形ROMカードを使うことが出来、それを4つまで自由に組み合わせてシンセサイズ出来るというところで、非常にリッチなサウンドを弾き出せるのは魅力ではありました。
《このシンセが聞けるレコードとは?》
ハッキリいって分かりません。これを使っていたミュージシャン自身が多くなかった上、特徴的なサウンドを持っていなかったためでしょう。これを使っていたのはエイジアのジェフ・ダウンズぐらいのものですが、彼も直ぐにこれを機材リストからハズしています。唯一「これじゃないか?」というレベルで確認できるのは元TAKE6のマーヴィン・ウォーレンがプロデュースした『ヘンデルのメサイア〜ソウルフル・セレブレイション』の中の「For Unto Us a Child is Born」でのベース、ドラムなど。
・ROLAND S-50 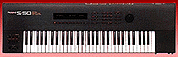
今や年代的にも古く、“ヴィンテージもの”になりつつありそうな12ビットのサンプリング・キーボードですが、「Peter宮崎道スタジオ」唯一のサンプリングできるマシンです。内蔵音源を持たず、サンプリング(目的の音を録音)して楽器音として使う以外何も出来ない反面、何でも音を取り込めば如何様にも使える手軽さがあります。12ビット・サンプリング/内部処理16ビットという中途半端な機種なので(いわばDATの“Long Mode”に於ける32KHz録音と同じ)現在のものよりもスペック自体は劣っていますが、サウンドは決してドンシャリにならず、中低域にシッカリした音が出る実に音楽的なサウンドを持ったサンプラーであり、重宝しています。CDではあまり多くのトラックでは使っていませんが、「こころのとびらをひらくと」(うしマ〜ク!版)のスティームオルガン、「きよきあさに」のパーカッション群等はここから出しています。
《みちくの余談》
1986年の10月頃に登場したこのROLAND初のサンプリング・キーボード、市場では大健闘を見せた名機でした。1985年当時はサンプラーといえば日本円にして200万円もしたE-MUのイーミュレーターや1千万円もしたフェアライトCMIであり、その高価な8ビットマシンと同等のサウンドを30万円程度で実現したシンセ市場の新参者エンソニック社の“ミラージュ”が一世を風靡したばかりでした。日本のAKAIもS612という12ビットマシンでこの業界に本格的に参入してきた頃です。1986年にはそのAKAIが12ビットマシンの決定版S900を出して大ヒットとなり、市場は本格的に安価な12ビットサンプラー時代に突入した時代です。コルグも素晴らしいシンセシス機能をプラスした12ビットマシンDSS-1を投入、大混戦となったものです。そんな頃、S900の発売から遅れること半年、満を期してROLANDから登場したのは12ビット・サンプリングながら16ビット相当の音質が得られるという“エクスパンデッド12ビット”というS-50、S-10でした。この2機種の音質の良さは即ち、供給されるサンプリング・データ自体の良さそのものであり、それは今も昔もROLANDのサウンドの強味です。
S-50は最初からRGB端子とビデオ出力端子を持ち、モニターを接続して使うことによって効率良いサンプリング/エディットが可能であり、電源投入時にはパソコンと同じようにOSを読み込んでから動作環境を作り上げる“クリーン設計”になっていました。そのお陰でOSソフトウェアによってはワークステーション化も可能になりました。そういう点で、サンプラー関係でシンセ市場に参入してきたパソコン系メーカー(エンソニック、ニューイングランド・デジタル等)が多い中、敢えてサンプラーを自社製音楽専用パソコンに見立てつつ、キーボードユーザーにはそれを感じさせないように設計したのは見事でした。それがウケて、その後もS-50の2台分の音源モジュールS-550、内部に内蔵音源やシークェンサーを搭載した“オールインワン”タイプの先駆けであったW-30、S-550とほぼ同じスペックのS-330、16ビットにグレードアップしたS-760等が続々と登場しました。いまだにサンプラーとえいば“S”(AKAIも同じSシリーズである)と決定づけたのです。
《この音が聞けるレコードとは?》
どこででも聞けますが、どこででも聞ける訳ではないと思います。モノがサンプラーだけに、固有の音を持たないからです。
・ROLAND JUNO-6 
1980年代に登場したアナログシンセのビンテージモデルです。DCO(Digital Controled Oscilator)という一時期流行った“デジタル制御のアナログ発信機”を備えており、音質的には決して“太い・芯のあるサウンド”は苦手ですが、音程が安定しているため、現在でも使いやすい逸品です。が、MIDI(Musical Instruments Digital Interface)登場以前のもののため、このスタジオでは滅多に使いません。しかしコードを押さえるとアルペジオ演奏する懐かしい“アルペジエーター”を備えており、今回は特に「パラダイス」のみで使用しています。
《みちくの余談》
このシンセは世界初のDCOという発信器が積まれたものでした。このDCOは従来のVCO(Voltage Controled Oscilater)の電圧の揺れなどによる音程の揺れやズレをなくすため、コンピューターに使用されるデジタルの「クロック回路」をもって供給される電圧配分を安定化させる、といったもののようです。それ故、かつての機種の問題であった“暖まってくるとチューニングが狂う”といった事がなく、電源投入時から絶対にピッチが狂わない事が最大の長所でした。が、実際に出てきた音はかなり細く、しかも電圧変化による不確定な「揺れ」がないため、このJUNO-6は当時としては非常に“デジタルな冷たい”感じがしました。しかし内蔵のコーラスは同社のDimention D並に素晴らしく、それが全ての欠点を補って余りあるものだったことは疑い用のない事実です。ある意味ではそのコーラスが素晴らしいこともあり、ソリーナ等のストリングス・シンセと同様な“パッド・サウンド系”を得意としました。面白いことにこのJUNO-6、当時はあまり個性のないシンセだったと思いましたが、現在では“とにかくメチャクチャ綺麗な音しか出せないシンセ”として、個性を放っています。
この後、JUNO-6にサウンド・プログラム・メモリーを搭載したJUNO-60、DCOに多少改良を加え、MIDIも装備したJUNO-106(スピーカー付きの機種も出た)、DCOの波形を増やして操作パネルからスライダーを取り除き、ダイヤル操作でパラメーターを呼び出して変更するα-JUNO1&2等、JUNOシリーズは変化を遂げました。
《このシンセが聞けるレコードとは?》
当時は“サウンドに個性がない”ということから、使われていてもどれがどれだかわからない、というのが現状でした。が、唯一いかにも、というのは、ハワード・ジョーンズの1st『かくれんぼ(Human's Lib)』の中の「雨を見ないで」でのパッド・サウンド(矩形波の音)です。当時H.ジョーンズはJUNO-60を所有しており、レコーディングでは頻繁に使った模様です。
・Fender CHROMA Polaris II 
80年代後期に登場したMIDI付きの純粋なアナログ・シンセです。シンセメーカーの老舗=ARP社直径の2つのVCO(Voltage Controled Oscilator)は非常に暗く重たく、しかもブワブワいいます。「きよきあさに」のシンセ・ホルンサウンドはこのシンセとYAMAHA DX-7との混合音です(左右に分けている)。しかもリング・モジュレーション、VCO同士のシンク機能等も備えているため、過激な音は非常に得意としています。「オーバーチュア:“Access To The Lord”」でのせり上がりの電子(電圧)音はこれです。更にグライド(ポルタメント)は予め設定した掛け具合を、サスティンペダルを踏むことによってオン/オフ出来るという不可思議な機能があり、グライドを多用している「踊らずにはいられない」や「Tell Me The Way」等のシンセベースはここから出しています。
《みちくの余談》
このシンセはCBS傘下から出た“CHROMA”というアナログ・ポリフォニック・シンセの名機のコストダウン版として登場しました。しかし元々CHROMA自身はシンセメーカーの老舗=ARPの起死回生の最後の切り札として設計され、システムシンセ並の複雑なソフトウェア・モジュレーションパッチングが組まれ、使い方によってはあらゆるシンセサウンドを生み出すことが可能な強力なシンセでした。が、生産ラインに乗る前にメーカーが倒産、エンジニアたちは何としてでもそれを発表したかったといいます。そのCHROMAがウェザー・リポートのジョー・ザヴィヌルやハービー・ハンコック等に大絶賛されたことがひとつの契機になったようです。実際、、ハービー・ハンコックはCHROMAを「これは素晴らしいレスポンスを持つ、紛れもない楽器である!」と各誌で豪語していました。そしてダウンサイジング・デザインされたCHROMA Polarisを発表、これがまたジョー・ザヴィヌルやチック・コリアに絶賛され、一時期はステージでも見られました。そのPolarisを日本販売する中で、国内生産に切り替えたことでコストダウンにも成功し、再登場したのがPolarisIIです。基本的な音色はどちらかといえば暗く重く、ストリングス・サウンドは独特の重みと優雅さを湛えています。フィルターも非常に美しく、鋭い音よりは軟らかいヴェールのかかったようなサウンドは絶品です。しかし一時リングモジュレーターを使えば強力に汚い音が出せ、サウンドの幅は圧倒的に広いのが特徴です。小さなデジタルシークェンサーも搭載してます。
しかしこのシンセがARPなのだとハッキリ分かる部分があります。音のアタック感、減衰を作り出すエンベロープジェネレーターが2機搭載されており、片やADSR、片やADRだということ。これはARP2600あたりから継承されてきたもので、一時期はARP派とも言えるROLANDが同じスタイルをJUPITER-8等で採用していました。又、グライド(ポルタメント)をかけたサウンドは、明らかにARPならではの“平均的になだらかに移行する”感触があり、プログレなどでお馴染みのMOOGのMINIMOOGなどの“最初フニャっと、あとは素早く”というのは質を事にしています。ある意味では非常に“テクノ”な感じと言えるでしょう。
・Kurzwell Ensenble Grande MK-III(Master Keyboard) 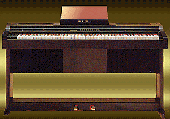
本来はホーム・タイプの電子ピアノですが、88鍵盤にプラスしてシンセサイザーに標準的に着いている“ピッチベンド”、“モジュレーション”の二種類のホイールがあることから、いつしかMIDIマスターキーボードとして活躍しています。有る意味ではMIDI初期のキーボードであるためか、鍵盤のヴェロシティ・センス(弾いた強弱を感知するセンサー)が常に高いのが特徴です。ここから音を出して録音することは今はありませんが、音はホームタイプとはいえ、かつてはプロなら誰もが手にしたがった名機カーツウェルK-250のサウンドがそのまま入っています。
・YAMAHA DX-7 
アナログシンセ全盛の時代の1984年頃に発売され、当時のシンセ業界の売り上げ販売数史上第一位を記録した金字塔的デジタルシンセです。スタンフォード大学のラボでドクター・チャウニングによって開発された“FM”(周波数変調)という理論に基づいたシンセシス機能を持ち、その音色は今でも立派に使えます。「あの日のこと」ではFMチューブラー・ベルズの音色が欲しかった事もあって久々に引っぱり出してみましたが、それ以後の録音モノではほとんど使っています。「きよきあさに」のPolaris IIとのシンセ・ホルンサウンド、「パラダイス」でのグロッケン的なサウンド(JUNO-6との混合)、「タリタ・クミ(少女よ起きなさい)」の高音域のグロッケン的サウンド、「主のもとへ帰ろう」のバックで鳴るシンセ・ストリングスともシンセブラスとも言いがたいパッドサウンド等、CDではかなりの頻度でその存在感を発揮しています。
《みちくの余談》
YAMAHAのFM音源キーボードの歴史は意外と古く、'80年前後にピアノタイプの2機種=GS1とGS2という機種で始めて採用されたと聞いています。これらは同社のエレクトーンの最上位機種“GX1”と同じように大型の専用スピーカーも含んだモノで非常に高価でしたが、YAMAHAのFMシンセシス・コンピューターを使えばオリジナルなサウンドも作ることが出来たそうです。ですが'82年頃にはその普及版と言えるプリセットキーボードを発売、これが業界で「信じられないぐらいリアルな音がする」という評判を呼び、その直後に登場したのが自分でパラメーターを変更してFMシンセサイズできるDX7とDX9でした。
DX7はMIDI黎明期の1984年当時のものとしては群を抜いてMIDIが安定している機種です。今でも出先ではこのシンセをマスターにして仕事したりします。プラスチックの鍵盤はヘタにウェイトをつけずに素晴らしいタッチを実現しているのも特筆モノです。いまだに仲間内では「DX7がシンセ鍵盤の最高だね」と話し合うものです。又、FMという小難しい理論からなる難解なシンセシス機能はいつも問題でしたが、理解すれば“白玉を弾いていても生きている音色=うねりのある音色”を作る事ができました。ステージ等で使う際、演奏のファンクションが豊富にあったことで表現に関してはまったく過不足なかったというのもいまだにスゴいと思わされます。あらゆる意味でこのシンセサイザーは、世界最高のものを持っていたと言えます。が、最大の弱点は6オペレータから成る1サウンドでは厚みに限界があったことで、その点は上位機種=DX−1、DX−5で、又DX−7IIで解消されていきました。更にDXシリーズは7と5では同じサウンドでも音の厚みが違いました。どうやら唯一のアナログ回路であるボリュームのパーツの質の違いだったようです。
DX−7シリーズの中で画期的だった事はMIDIの利点を生かして次々と鍵盤のない心臓部のみの「音源モジュール」を開発したことです。そしてこの発想はMIDI黎明期にも関わらず、DX−7のサウンドボード8枚分を装着したFM音源モジュールの王様“TX−816”を生み出しています。
しかしスタンフォード大のラボからパテントを取り、同じFMシンセシスを導入した音源部を持つシステムは他にも存在しました。代表的なところではニューイングランド・デジタル社の“シンクラヴィア”でしょう。このシステム・キーボードは始めはFMシンセサイザーとして出発したようですが(富田勲や“ジェネシス”のトニー・バンクスが使用していたシンクラヴィアIIが有名)、次第にサンプリング機能を付加、'85年頃にはサンプラー+FMシンセシスを音源部に持ち、パソコンによる集中管理によりシークェンサー/譜面作成機能等があり、更にはディスクメディアによる巨大なデジタルレコーディングワークステーションへと変貌を遂げました。シンクラヴィアでのFMシンセシスについてはYAMAHAのTX−816が数台分詰まったようなシステムがあり、本体内コンピューターのフーリエ変換ソフトウェアによってサンプリングされた音をフーリエ解析、時間軸で縦割りにしたパーツをFMシンセシスによって再現し、その時間軸に沿って順次再生するという“リシンセシス”という機能でも使っていました。私は当時神楽坂にあった“スタジオゆりーか”でシンクラヴィアのフルセット(1億5千万円もする巨大なシステムでした)を使う事がありましたが、そのリシンセシスによるサウンドは、サンプリングとは違う独特のリアリティーを持っていたのを覚えています。FMシンセシスの可能性は限りなく広いことを実感したモノです。
《このシンセが聞けるレコード?》
DX7は大ヒットしただけでなく、誰もが好んで使ったため、いくらでもあります。最もヒットした楽曲でこれが聞ける、という点でいえば、ホイットニー・ヒューストンの2枚目『ホイットニーII』では数々の大ヒットバラードでDX7のFMエレクトリック・ピアノ・サウンドが聞けます。又、玄人好みのマニアなところでは元マハビシュヌ・オーケストラのヴァイオリニスト、ジェリー・グッドマンのプライベート・ミュージック・レーベルからの1st『未来飛行(On The Futue of Aviation)』のタイトル曲で、ファクトリープリセットのチューブラー・ベルズ・サウンドがのっけから聞けます。
・YAMAHA P-150(Digital Piano)
ステージ用に使っている電子ピアノですが、今回はレコーディング用にセットしました。心臓部の音源は同社のホームタイプ=クラビノーバ・シリーズと同じです。如何にも“ヤマハのコンサートグランドよ”と言わんばかりのシャープな立ち上がりはロックやジャズ等に向いています。ピアノの入っている曲のピアノサウンドは、ほとんど全てこれで出しています。
《みちくの余談》
私は基本的にはヤマハのデジタルピアノはあまり好きではなかったのですが、これをステージ用にと買ったのには、スピーカーが内蔵されたコンパクトタイプのものはこれぐらいしかなく、そこから出る音が非常に良かったからです。しかし元々録音用の“レコーディング・チューニング”されたものではない“ストレッチ・チューニング”であるためか、「主のもとへ帰ろう」の冒頭にあるようにハイノートでは他の楽器とチューニングがズレてしまうようです。これも一つの問題ですね。
・YAMAHA YC-45D(Combo Organ)
ヤマハ・エレクトーン部の一部のエンジニアチームが組み上げたという幻のコンボオルガンです。エレクトーン独特の音色を持つタブレットと平行して並んでいる正弦波らしき音を発生するドローバー・タブレットがあり、このタブレットの正弦波は“ブライトネス”というタブレットを手前に引くと矩形波に近い音になり、その音でドローバータブレットを組み合わせると、まるでチープな電気オルガンのサウンドになります。現在は「品川みちくのスタジオ」への引っ越しの際、鍵盤の状態が悪くなってしまったのでほとんど使えませんでしたが、「こころのとびらをひらくと」(うしマ〜ク!版)の半音階的に上昇・下降するフレーズをこのオルガンを使い、“チープな音”で弾いてレコーディングしました。が、CDのための最終ミックスでそのパートはカットしたため、実際的に使われていない事になってしまいました。
《みちくの余談》
これは70年代中期に登場したコンボオルガンの名機です。見かけはエレクトーンの「タブレット式」ですが、ハモンド・タイプの正弦波を組み合わせる“ドローバータブレット”(波形は本当は矩形波。フィルターが付いていて、開けるとチープなVOXオルガン風になる。GSはこれでOK)、エレクトーンと同じ音色のタブレット、それらに対して効果を発揮する“ファズ・タブレット”(内蔵ディストーション。これでハードロックもOK)、それに加えてピアノ、チェンバロ、マリンバ、ビブラフォンといった特殊音色を備えているだけでなく、黄色のタブレット(ピアノやチェンバロ、エレクトーンタブレットの一部)は下鍵盤右に付いている“タッチレスポンス・スイッチ”をオンにするとタッチで強弱が付けられるという画期的なものです。最上部にはソロ鍵盤の代わりなのか、不思議なリボンコントローラーが装着されています。これは独自に音程を取ったり不可思議なグライド・サウンドを奏でたりする事が出来ますが、発想としてはフランスのモーリス・マルトゥノが1920年代に製造した電気楽器“オンド・マルトゥノ”と似ています。
《このオルガンが聞けるレコードとは?》
実はこのオルガン、日本国内ではなく、海外ミュージシャンには最高の評価を与えられたものでした。私の知る限りではフュージョンで多く用いられていたようで、ジャズ・ヴァイオリニスト、ジャン=リュック・ポンティのアルバム『エニグマティック・オーシャン』でアラン・ザヴォーの弾くこのオルガン(どう聞いてもシンセサイザーと聞き間違うほどエレクトリックなサウンドを出している)を聞くことが出来ます。変わったところではミニマリストのテリー・ライリーがこのオルガンをこよなく愛する1人であり、純正律にチューニングして即興演奏を繰り広げた『シュリー・キャメル』で存分にこのオルガンを聞く事が出来ます。
・KORG POLY-61 
スタジオ内で唯一のコルグ製品です。パネル上のスライダーやノブをほとんど排除し、ディスプレイとスイッチで目的のパラメーターを変更する“パラメーター呼び出し式”の先駆け的存在でした。が、そのため、操作性は圧倒的に悪いのが特徴です?!。2つのDCOを備えていますが、信じられないほど細い音が出る上、その音程の安定度は群を抜いて素晴らし過ぎます。それ故、2つの同じ波形をデチューン(互いに少し音程をズラす)させても機械的聞こえます。更にVCFはあまりに美しく出来上がってしまい、どうしても荒々しい音は出せません。これは“チープの権化”です。「こころのとびらをひらくと《うしマ〜ク!》」(日本聖公会・古今聖歌集増補版'95)で使うつもりで引っぱり出してみましたが、鍵盤の状態が思わしくないため結局は使えませんでした。
《みちくの余談》
このシンセサイザーが出た頃は、日本ではコルグとROLANDという2大シンセメーカーがしのぎを削っていた興味深い時代でした。POLY-61登場以前、コルグのシンセで最も手頃な値段で市場に登場した1VCOタイプの6ボイスのポリフォニック・シンセサイザーPOLY-SIXは大成功を収めました。それに対抗してライバルのROLANDは同じランクの1DCOの6ボイス・ポリフォニック・シンセJUNO-6を送り込み、市場は大混戦となったのです。それ以前にプロ仕様の機種の世界ではアメリカのシークェンシャル・サーキットの“プロフィット5”に追いつけ追い越せとばかり、ROLANDはJUPITER-8(シンセ史上の名機)で大成功を収め、一方コルグはトライデントで失敗していました。ここで日本メーカーの独壇場=安価なシンセ作りの面で成功したPOLY-SIXで名誉挽回したのに追手が現れた事で焦ったのか(??)、2DCO仕様音づくりの幅を広げ、来るべきデジタル時代を先取りした先進的なデザイン(当時老舗MOOGの“SOURCE”がパラメーター呼び出し式的なアイディアをデザイン、その後にCBSのバックアップで登場したCHROMAがその先駆を付けた)を採り入れ、メモリー出来る音色数も64という(当時としては)膨大な数を持たせたこのPOLY-61を市場に投入しました。結構売れたようですが、しかししょーもないこの音はあまりウケなかったようです。更に何とこのシンセが出た翌年に、シンセの歴史上で最も画期的な提案であった「MIDI」が登場、そのMIDI端子標準装備の第一号シンセとして、ROLANDはPOLY-61への対抗機種“JX-3P”を投入してきました。音の差が歴然としていた上、MIDIも付いていることからこの時既にPOLY-61は悲劇のシンセとなってしまいました。しかしコルグはこの直後、更に安くて多機能、小さい上に音も太い“POLY-800”で挽回したのです。この当時、コルグはいつも安値のフロンティアでした。
《このシンセが聞けるレコードとは?》
私が知っている限りでは、ただ1人だけのレコードで確認する事が出来ました。当時コルグとエンドースメント契約していた、元イエスのリック・ウェイクマンのソロアルバムです。「静夜」と「リック・ウェイクマン・ライヴ」の二枚ではPOLY-61独特のチープな音でバリバリとソロを弾きまくるウェイクマンが、ちょっと情けないです。
話によるとこの当時、ELPを解散して映画音楽業界に進出していた巨匠キース・エマーソンもコルグと契約しており、角川映画『幻魔大戦』でのサウンドトラック(名曲「光の天使」を含む)で聞けるシンセサウンドは全てコルグ製品だということですが、POLY-SIXやトライデント、MONO/POLYなどのVCOタイプのアナログシンセを駆使しているサウンドはなかなか美しく、深淵です。リック・ウェイクマンの80年代のアルバムとは大違いのサウンドを出しています!!
・SOLINA Strings Ensemble
オランダの“ソリーナ”から出ていた電子式ストリングス・キーボードです。世界的に大ヒット、ロングセラーを続けた逸品で、独特の冷たいサウンドが70年代アメリカのフュージョンやAORでは大ウケしていました。このキーボードは「オーバーチュア:“Access To The Lord”」の中間部(「たたえよ主を」の旋律挿入部)で使うつもりで引っぱり出してきましたが、結局はROLAND SC-88で代用したため、使わすに終わってしまいました。勿論MIDI仕様ではないため、使うとなると手で弾くことになるわけですが、今は自分でROLAND S-50にサンプリングしてあるため、サウンド自体は使うことが出来ます。今回使わなかったのは、そのサウンドが余りに個性的過ぎたためです。
《みちくの余談》
このキーボードは何故か社名をそのまま呼んでいました。しかもストリングス・アンサンブル・キーボードといえば“ソリーナ”だったものです。不思議なことにこのキーボードは弦楽器セクションの代用品として作られた訳でもなさそうなのですが、高音部を白玉で、ボリュームペダルを使って奏でるとホンモノと聞き間違うほどリアルに響いたりします。
当時の日本レコーディングスタジオ事情では、ひとつの論争があったようです。このキーボードとは全く発想が違うストリングス代用マシンに“メロトロン”という、今でいう“サンプラー”の元祖的な磁気テープ式のサンプリングキーボードがあり、ソリーナはいかにも電子音ですがコンパクト(そりゃー重たいけど)で頑丈、片やメロトロンはサスガに録音音源の再生という超リアルな音色を持っていましたが頻繁に持ち運ぶにはあまりに重たくデカく、メカニック的にも繊細で壊れやすいという弱点もありました。しかし両者とも面白いことに、その音をアンサンブルの中に加えるだけで、トータルサウンドカラーを一変させるほどの超強力な個性があったことです。
《このキーボードが聞けるレコードとは?》
70年代フュージョンやAORを聞けば必ずといっていいほど聞くことが出来ます。サウンド的に重たくなく、使い方によっては爽やかな音色も出せることから比較的アメリカでウケたようで、ハービー・ハンコックなども使用していました。ヨーロッパのプログレ・シーンではメロトロンばかりでしたが。
・ARP 2600 
超ビンテージモデルといえる、システム型モノフォニックシンセの名機です。スタジオには常に使えるように常設してありますが、今回はアナログシンセのPolarisIIとEMS AKSで100%OKだったので、使用は控えました。
《みちくの余談》
アラン・R・パールマンの「ARP」といえばロバート・モーグの「MOOG」と並んで、ミュージック・シンセサイザー黎明期の2大老舗メーカーでしたが、80年代に両者とも倒産しています。このARP2600はトランクタイプのケースに収納されている3VCOタイプのモノフォニック・システム・シンセサイザーで、スタジオやミュージシャンに大ウケしただけでなく、ユーザーズ・マニュアルが音の要素、原理からシンセサイザーの基礎知識、シンセシスのやり方などをも内包した素晴らしい書物であったことからか、学術・学校教育用にもよく売れた機種だったそうです。MOOGシステムシンセが各種モジュール完全独立でバラけているため、いちいちモジュール間をシールド(パッチコード)で決線しなければならないのに対し、ARP2600は予め基本的な音の流れが内部結線されており、必要に応じてモジュールに付いているプラグ同士を結線することで煩雑さを解消しています。そのサウンドカラーはシャープで、いかにも“電子音”といった趣です。しかしやはりシステムシンセの恐ろしさは、如何様にでもモジュレーションを組めるというところで、同じアナログシンセのPolarisIIも到底適わないものがあります。
ところでそのPolarisII、実は調べてみればARPの末裔であったのは驚きました。確かにARP2600とPolarisIIのサウンドカラーはよく似ています。それ故、通常のシンセサウンドを得る場合にはPolarisIIを使い、そうもいかないサウンドが欲しい時には2600に電源を入れる、という具合に使っています。
《このシンセの聞けるレコードとは?》
これも70年代初頭〜中期にはシンセサイザーの入ったレコードではどれでも聞く事ができましたが、主にヨーロッパ系のミュージシャンがよく使っていたようです。特にフランスのジャン=ミッシェル・ジャールの1stアルバムでは“ARP2600そのもの”といった音色が随所で聞かれます。
・EMS AKS 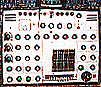
イギリスの古いシンセサイザー・メーカーで最も有名且つフレキシブルなこのメーカーのこの機種、スタジオにあるものは実はキーボード(プリントパネルのタッチキーボード)が壊れて使えないため、正式には音源部のみの製品“SYNTHI A”といえます。3VCOのモノフォニック・システム型シンセであるにも関わらずブリーフケースサイズというのも珍しいのですが、もっと珍しかったのはX−Yコントローラー(ジョイスティック)が装着されていた事です。このコントローラーを如何に使うかによってSYNTHI Aは鍵盤を不要とするほどの面白さを実現してくれます。CDの中では「オーバーチュア:“Access To The Lord”」で使いましたが、左右に飛び交う、いかにも電子ノイズの嵐といったものに使用しました。3つあるうちの1つのVCOを残り2つに“モジュレーター”(変調をかける側)として用い、コントローラーにはX軸にVCF(フィルター)の開閉を、Y軸には音の出ている2つのVCOのピッチ可変を割り当て、コントローラーをグルグル回して「演奏」しています。又、冒頭のクラリネットではサンプラーから出したペケペケしたクラリネットサウンドを外部入力端子からVCFにインプットし、フィルターを手で開閉することで表情を付けています。
《みちくの余談》
EMSの製品には幾つか種類がありましたが、基本的にシンセサイザーはSYNTHI Aを心臓部に持つインターフェイス違いのものだったようです。AKSはブリーフケース型でタッチキーボードが付いていましたが、少々大型の“VCS3”は通常の鍵盤を付けて演奏する場合が多く、ロックではこのVCS3を使うミュージシャンが多かったように思います。このシンセの小型軽量化の成功には、大変画期的な“マトリックス・パッチングボード”というものが挙げられます。これを専用のピンを刺してモジュール同士を結線しないと音が出ないのですが、かなり自由にモジュレーション・ルーティングが出来ます。又、デジタルシークェンサーも内蔵しており、鍵盤が生きていれば入力して使う事ができたのですが......。
《このシンセが聞けるレコードとは?》
このシンセ、あまり手で演奏されることは少ないようです。古くはピンク・フロイドがアルバム『狂気』の中の「走り回って」で使用した、デジタルシークェンサーを使ったあの音が印象的です。この時のレコーディングの模様はビデオ『ピンクフロイド・ライヴ・アット・ポンペイ』でも確認する事が出来ます。ジャン=ミッシェル・ジャールに至っては10台ものSYNTH A、VCS3を壁状並べ、楽曲の中でX−Yコントローラーを使って様々な電子ノイズを出すというリアルタイム演奏をやっています。ライヴアルバム『コンサート・イン・チャイナ』のライヴ映像ではそれが確認できました。J=M.ジャール同様、現在もこれを使用している1人にブライアン・イーノがいます。
・ROLAND SC-88(SoundCanvas) 
GM/GS音源の名品です。ズバリ、このCDのメイン音源です。アレンジの作業としてはまずこの音源に完全対応させて全パートをアレンジし、正式なバック・オケ録音の際に他の音源にパートを“差し替える”という方法で行いました。CD製作に当たっては録音用と平行して楽曲のMIDIデータも製作するという目的があったため、SC-88は正にうってつけの音源だったわけです。バック・オケの入った曲では全曲で使っています。特に2曲の「こころのとびらをひらくと」で、うしマ〜ク!版では純正律チューニングを施して演奏していますし、P&J版の方では2本のアコースティック・ギターはここから出しています。ギターといえば「あの日のこと」のアコ・ギもこれです。とにかく便利な音源です。
《みちくの余談》
DTM(Desk-Top Music)の世界では標準化されたフォーマット、GM(General MIDI)規格はそもそもROLANDが提唱したものでした。D-50やS-50といったデジタルキーボードを開発し劇的に売りまくる反面、DTMについて最も早くから真剣に取り組んだROLANDは偉い。GM規格そのものは同社のD-10のプリセット音源ともいえる小型のMT-32というものがひとつのお手本になっているようです。ちなみにGM規格とは、音源側の音色の並び方を定義したもので、MIDIのプログラムチェンジ・ナンバーの0〜127(1〜128)に対応したものです。128種類の音を規格通りに音源側が並べていれば、基本的にはMIDIデータに互換性が生まれるだろう、そういう発想でした。
1986年、ROLANDはDTMの業界(まだそんな名前はなかったが)ではNECのパソコンPC9800用のシークェンス・ソフトを販売していましたが、ここに参入してきたのは大手のYAMAHAでした。DX-7で大当たりを出したYAMAHAはMSXパソコンを発表、それにDX-9/21/100相当のFM音源ボードを装着したマシンが売り出され、次いで豊富なプリセット・サウンドを有した小型軽量の音源FB-01を市場に投入しました。このFB-01こそDTM音源の先駆けともいえる音源で、これに対抗する商品(??)としてROLANDはMT-32を発表したと思われます。しかし両者の違いは、FB-01が“MIDIの拡張音源・最も安いFM音源”、MT-32が“パソコンと繋いで使ってほしい音源”というというコンセプトが見えたことでした。
MT-32がGM規格のお手本になったことで、ROLANDはその先駆者として徐々にGM規格対応のものを市場に投入します。しかしROLANDはGM規格自体のサウンドバリエーションの幅のなさ(GMでは音の並びぐらいしか定義されていない)を解消するため、GM規格上でNRPR(ノン・レジスタード・パラメーター)等を使って内蔵のフィルターやエンベロープ・ジェネレーターを動かすなどの細かな設定ができる独自の“GS規格”を打ち出しました。その結晶が“サウンドキャンバス”SC-55でした。このSC-55の心臓部は色々なところで流用され、設定がマニュアルで簡単に出来るスライダー付きのもの(SC-155)、全くつまみのない箱だけのもの、鍵盤がついたもの等が登場しました。その後直ぐにアップグレード版のSC-55mkIIが登場、これは事実上のGS音源のスタンダード機となりました。これと同じ心臓部を持ちながらかなりプレイヤビリティを追求したシンセサイザーJV-30というのも登場しました。が、更に今度はSC-55mkIIの音色を再検討してパワーアップして登場したのがSC-88でした。サウンドキャンバス最上位機種に相応しく、余裕の64音ポリ、2系統のMIDI IN、設定によってはSC-88の心臓部を独立2台分に分ける事さえできました。GS音源としてある種のシンセシス機能を充実させるため、内蔵サンプル波形はかなり変更が加えられた事でこの音源の可能性は飛躍的に高まりました。これが現在のGMタイプの音源モジュールの事実上のスタンダードだと言えます。ROLANDはこれに手を加え、薄型軽量にしたSC-88VL、更にパワーアップしたSC-88pro、心臓部のみをパソコン上に再現したVSC-88等を次々と発表しています。
・ROLAND MV-30 
スタジオに1994年にMacintoshが導入されるまで、この通称“STUDIO-M”はマスターキーボードKurzweill Ensemble Grande MK-IIIと共にスタジオのMIDI機器の中枢でした。これは鍵盤のないワークステーション、というよりは音源を内蔵したシークェンサーで、非常に重宝したものです。今はMacintoshにとってかわられ、普段はステージでシークェンスを走らせる“もう1人のメンバー”となっていますが、今回は特にパンくず・喜多京司氏の作品に使用しています。氏もMV-30を所有しており、私達はこれを通じて演奏データと、正確なイメージのトータルサウンドを共有出来たのです。使った曲は「踊らずにはいられない」のギター、「Tell Me The Way」のノイズまじりのスウィープサウンド等、限られています。これらのサウンドは喜多京司氏によって作られたものです。
《みちくの余談》
ROLANDは1台である程度何でも出来る“ワークステーション”という思想をかなり早くから取り入れたメーカーであったといえます。その最初の形がクリーン設計のサンプラー=S-50であり、W-30であったと思われますが、その流れはその前からありました。同社の2つの製品を合体させ1つにまとめる、というものです。この手のマシンは悪く言えば生産をストップさせる直前にそういった古い製品の残りボードを効率よくさばくための策であったとも言えるかもしれません。
シークェンサーと音源を合体させる、というMV-30“STUDIO-M”の発想の源流は既に1980年代にはMC-202というマシンで既に実現していました。これは同社が70年代に出してデジタルシークェンサーのスタンダードとなったMC-8/MC-4の流れを汲むシークェンサーに、同社の最後のアナログ・モノシンセ=SH-101の音源をプラスしたものです。この路線はある種ROLANDの専売特許のようなもので、その後もこういった製品は作られ続けています。このMV-30も、同社のシークェンサー=MC-5に、D-70の音源部(サンプル波形)をプラスしたもので、この基本設計とMT-32のGM的発想を組み合わせたのが、後の“GS規格”といえるかもしれません。
MV-30はD-70の音源部を持ってはいたものの、同社のプリセットサンプラー=U-220用の波形ROMカードをそのまま使え、D-70とは違いそこに収められたプログラムまで読み込んで使うことが出来ました。そういう点でシンセサイズ機能的にはD-70に及ばないものの、使い勝手は圧倒的に良いものです。このマシンはほとんど売れなかったと聞いていますが、使ってみないとその良さが理解できない、という堅実な地味さが災いしたようです。ルックス的にも音的にも派手であったコルグのM1やYAMAHAのSY-77が既に市場を席巻していた時でもあり、MV-30は時期的にも最初から苦戦を強いられたというのも理由としてあるでしょう。しかしサスガにライヴ・パフォーマンスに威力を発揮したD-70を送り出した直後のROLAND、このMV-30もライヴ用シークェンサーとしては最高のものを持っています。楽曲を並べ、1曲が終わったら直ぐに次の曲を読み込み、スタートするのを待っているという“チェインロード”という機能です。私たちのステージでは敢えてMacintoshを使わずにこのMV-30を使っているのは、その優れたライヴ・パフォーマンス(?!)があるからです。
・YAMAHA TX-81Z 
YAMAHAのFM音源です。この音源は常にスタジオのラックに収まっており、常に現役で活躍してくれています。これ単体で使うことはほとんどなく、何か他の音源やキーボードのサウンドと合わせて使います。よく使うのがFM音源らしいガーガーいう汚いパイプオルガン・サウンドを、ストップの“ミクスチャー”に見立て、D-70でシンセサイズした美しく荘厳なパイプオルガン・サウンドに加える事で重厚なオルガンサウンドを作ります。「きよきあさに」、「わたしはここにいる」等のパイプオルガンの入る曲では必ずといっていいほど、この手法でこの音源を使っています。
《みちくの余談》
1986年に登場したこの音源、DX-7の6オペレーターに対し、発信源が2つ少ない4オペレーター仕様で、同社のDX-9/21/100と似ていますが、決定的に違うのはオペレーターが発信する波形がFM音源の常識を覆す(?!)、サイン波以外の倍音を含んだ波形8種類を用いたことです。これにより、DX100等よりもずっとシンセサイズの幅が広がっています。しかし出音自体はやはり6オペレーターの充実感には及ばず、基本的TX-81Zは“複雑な可愛らしい音”を得意としています。しかし早くからマルチティンバーにも対応しており、音源としては充実しています。かつてはDX-7と併用する拡張音源として使っていたミュージシャンも多かったようです。
・E-MU Vintage-Keys 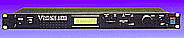
私にとって、どこでも持っていく素晴らしい逸品です。基本的には“イーミュレーター”でサンプラーの世界で先駆をつけたアメリカのE-MUらしく、内蔵波形は“プリセットサンプラー”と言っても過言でないほど充実したサンプルが入っており、その名の通り古い電気キーボードが盛りだくさんです。ハモンド・オルガンやメロトロンといったサウンドが素晴らしいため、その手のサウンドで使う事が多いです。今回のレコーディングでは「躍らずにはいられない」、「あの日のこと」等、ハモンドオルガンが聞かれる曲では全てここから出しています。その他「主のもとへ帰ろう」でのサンプル&ホールドでモジュレーションされたシンセサウンド、「わたしはここにいる」のCP-80(エレクトリック・グランドピアノ)などもこれです。
《みちくの余談》
E-MUは70年代には大型のアナログ・シンセを開発していた純粋なシンセメーカーでしたが、デジタル・ディバイスの開発にも積極的で、70年代後半から80年代初頭にかけてはシンセ業界を陰で支えたメーカーとなります。そのデジタル技術を生かして製作されたデジタル・サンプラー=イーミュレーターは“サンプリング”という音響物理学的な専門用語を一般にまで浸透させるほど話題になり、“サンプラーのE-MU”という認識を決定づけたのです。その後、改良され音質も向上したイーミュレーターII、更には大幅なコストダウンを計ったE-MAXやE-MAX IIも市場に投入、そして16ビットマシンのイーミュレーターIII、イーミュレーターVIとグレードアップしていきました。が、その一方で豊富なサンプル・サウンド・ライブラリーを厳選し、1台の音源モジュールに集約したプロテウスが爆発的にヒットし、これは目的別にシリーズ化されていきます。オーケストラ楽器に集中した“Orchestra”、エスニック楽器に集中した“World”等です。これに気を良くしたE-MUは、続いてヴィンテージ・キーボードの音源を発表するに当たり、例えばMOOGのMINIMOOGの原波形やバリエーションを使ってユーザーが自由にシンセサイズできるよう、独自のフィルターやエンベロープ・ジェネレーター等のシンセ機能を搭載させ、このVintage-Keysを発表しました。それまでサンプラーでしか音ネタがなかった60年代のテープ式サンプラー=メロトロンやチェンバリン、70年代にスタンダード化したYAMAHAのエレクトリック・グランドピアノ=CP-80、ローズからウーリッツァーまでの各種エレクトリック・ピアノ、他社から単体の音源としてまで発売されていたハモンド・オルガンB3等の音色を1台から出せるというのは画期的な事でした。しかもMOOG, ARP, Oberheim、シークェンシャル・サーキット、日本のROLAND等、往年のシンセメーカーのアナログシンセからサンプルしたサウンドや波形も搭載され、非常に充実した“シンセサイザー”となっています。
E-MUはここで再びシンセサイザーに目覚めたのか、モーフィング・フィルターなるものを搭載したシンセサイザー音源Morpheusを発表するなど、元気にやってます。70年代に登場したアメリカのシンセメーカーでは、社名だけが残ったOberheimと並んで第一線で生き残っている数少ないメーカーの1つです。
・AKAI CD3000 
CD−Rやフロッピーを読み込み、使うだけの“ステレオ・プレイバック・サンプラー”です。別売りされている様々なオプションを取り付ければ自分でサンプルが出来るのですが、私はそれを持っていません。それでも尚、このサンプラーは魅力的なものです。基本的には本体付属の5枚のCD−Rと、幾つかの市販サンプルデータ・フロッピーを使用するだけです。このCDでは「オーバーチュア:“Access To The Lord”」の電話のプッシュ音、「踊らずにはいられない」、「パラダイス」、「Tell Me The Way」、「タリタ・クミ」、「主のもとへ帰ろう」、「わたしはここにいる」、「たたえよ主を」のストリングス・セクション、「たたえよ主を」のグランドピアノ等はここから出しています。特に人工的でない広がりのあるステレオサウンドのストリングス・セクションは、現スタジオではこれ以外では出せません。そのストリングスにソロ・ヴァイオリンをプラスしたのは「あの日のこと」のイントロです。悲しいほどに美しいこの曲のイントロの全てはこのマシンによります。又、「こころのとびらをひらくと(P&J版)」のフルートもこのマシンのサンプルであり、「オーヴァーチュア:“Access To The Lord”」のギターはエレキギターの生音のサンプルにVS-880の内蔵エフェクトボードでディストーションをかけたものを使っています。
《みちくの余談》
AKAIは1986年に12ビットサンプラーの名機S900を発表して以来、Sシリーズとして幾つものサンプラーを世に出してきましたが、1993年に16ビットサンプラーのスタンダード機ともいえるS3000でひとつの頂点を迎え、その心臓部を同社初の“プレイバック・サンプラー”であるCD3000に譲りました。これは一つの時代を象徴していたかもしれません。それまで12ビットの時代に海外の他社製品ではプレイバック・サンプラーは既に出現していましたが、日本のAKAIやROLAND等はCDクォリティーの16ビット/44.1KHzサンプリングまで待っていたようです。懸命ですね。
S3000やCD3000等、AKAIのSサンプラーシリーズは基本概念がアナログシンセのようで、そのシステム構成は非常に分かりやすい。基本的には4つまでサンプル波形をレイヤー出来ることから、ノコギリ波等のアナログシンセ波形を並べればMOOGのMEMORYMOOGよりオッシレーターが1つ多くボイス数も滅法多い、4VCO・32音ポリのシンセサイザーに変身するという寸法です。実は私はこれに魅了された、というのはあります。実際はそういう風には使っていませんが....。
現在のサンプラーは固有の音源波形を持たないデジタルシンセサイザーという色合いが濃いわけですが、このCD3000も同様です。積極的に音づくりをすれば、非常に味わい深いサウンドも得られます。そういう意味で、非常に良い“音のパレット”と言えるでしょう。
【Synthesizers/Keyboards】【Other Instruments】【Recording Equipments】
|